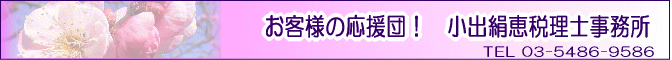
| �z�[�� |
| ���q�l�̐� |
| �������ē��} |
| ���₢���킹 |
| ���������� �T�[�r�X |
| ���M���e��� |
| ����������� |
| �o�c�~�j�m�� |
| �ŋ�Q��A |
| ���𗧂� �����N�W |
| �l���Ɋւ��� �戵�ɂ��� |
|
��v������ �V�l���L �m������i���o���b�j��� �����̎������i���o���b�ŗ��m�������j�̋Ɩ����e���A �ŗ��m��T���Ă��関���̂��q�l�ɒm���Ă��������̂ɍœK���ȁH �����̎������̂��q�l�ɂ��A�������ł̐V���E�����C�� �ǂ��������ɍs���Ă���̂���m���Ă����������Ƃ��K�v���ȁH �������ɉ�������V�������Ԃł����ł̌��C�����A ����ȑz�������Ɋ��������Ă��ꂽ���̂ł�����A �{�l�̗����āA�����ɍڂ������Ă��������܂����B |
|
������č��Ƃ�
��� �e����v����������芪�����ω��Ƃs�j�b��v�l�̎��g�� �ŗ��m�̎g���Ə���č� �s�j�b�V�X�e���̊T�v �����o���w���̃|�C���g ����č��̎��� �e�w�Q�̊��p �� �ኴ �z�� �ђ˖��_��̓�����q���o�������Ƃ������̎��n�������B��́A���{�Ŗ���v�ւ̋����M�ӂ����������m�ꂽ�B���̂��Ƃ͍���A���̎����̑傫�Ȍ��ƂȂ蓹�ƂȂ�Ɗ�����B �܂��A�s�j�b�V�X�e���̊T�v�����ނ��Ƃ��o�����B �֗^��l�Ƃs�j�b����������A�s�j�b�������Z���^�[�̑��݊W���G���g���A�e�w�Q���ꂼ���G�c�ł͂��邪�c���������B �s�j�b�͒��N�ɘj���Ė@�ߏ�����m�ۂ��A�m�������Ă���̂��ƁA�N�\�Ȃǂ��犴����ꂽ�B �\���̂o�b���A�d�q�\�����ȂǎЉ�̗���ɑ��Ă����������g�݁A��ɓ��{�̐Ŗ������[�h���Ă��āA�܂�ō��ɂ܂ŗ����Ă���悤�Ȉ�ۂ����B ��������č��⏑�ʓY�t�̗��s�ȂǁA�Ɩ��̂��ׂĂ��ŗ��m�@�����������ɂ��A�ŗ��m�g����S�����邱�Ƃ�Nj����Ă���̂��Ɗm�M�����B�搶���A�E���̕��X�S���Ɂg�ւ�������Ďd�����������h�Ƃ����ӎ��̋��ʉ����}��Ă���悤�Ɏv���B �፡��̔��W�� �s�j�b�̖��ɒp���Ȃ��d�����������B�p���l�`�r�⌈�Z�A�����ȂǑ����̎d�������邪�A�������u�������ߏ���I�m�ɏ��������邱�Ƃ����q�l�����v�Ƃ������Ƃ��ӎ��������A�Ɩ��ɔ��f�����Ă����w�͂�ӂ�Ȃ��悤�ɂ���B������\���ӂ܂�����ŁA�č���p���l�`�r�ȂǁA���ړI�ɂ��q�l�̂����ɗ��������Ɗ肤�B �܂��͎��͂𒅂��邽�߂ɂ��A�ǂ�Ȏd���ł��^�����ϋɓI�Ɏ��g�݂����B ���s�j�b�����s�S��H����w �Q��
��� �e��
�s�j�b�̌o���A���ʁA����̖ڕW�E�������搶���̂��b �u�`1 �F �ŗ��m�ɋ��߂邱�� �` ������Ƃ̃z�[���h�N�^�[ �` �啐����Y�搶 �u�`2 �F �ׂ����Ђ̂����� ���R���搶 ������Е����� �В� ���Z�v�V���� �ኴ �z�� ���ɗL�Ӌ`�Ȏ��Ԃ������B ����������łȂ��A�Q���ґS���ɂ����邱�Ƃł���B ����Ȃɂ�����Ȑl�I�l�b�g���[�N�����s�j�b�Ƃ́A���̉�v�������Ƃ͈�����悵�����g�D�ł���A�܂��Ɂu��z�v������v�l�W�c�ł���ƒɊ������B���̂悤�ɐ���Ȓm�I�𗬂̍Â����s�����Ƃ́A�ΊO�I�ɂ����ŗL���ł���A���Ԃɂs�j�b�̑��݊���F�m�����邱�Ƃɂ��q����Ǝv���B �������������͐�����Ȃ����A�����Đ��_�q�ׂ�Ȃ�A���ɂ͎����x�̎҂ɂ����̐搶�����l�ɖ��O�̃v���[�g��p�ӂ��Ă�������A���̈ē��A�p���t���b�g�����������������Ƃ��B�[�X�̎҂܂Ō����Ƃ����ɒ��J�Ɉ����A����͑S������M�d�Ȏ��Y�Ƒ����A��ĂĂ����A���ʓI�ɂ��q�l�ɊҌ��ł���悤�Ȏd�g�݂Â���ɒʂ���Ǝv���B�����ɂ���̂͂�͂�u���������v�̔ђˉ�̐M�O�Ȃ̂��Ɗ������B ���ɂ͂s�j�b�͓d�q�\���E���ʓY�t�̃��[�_�[�I���݂Ȃ̂��Ƃ́A�P�������������o�������Ƃ��B �d�q�\���E���ʓY�t�ɂ����Ăs�j�b���ǂꂾ��������o�Ă��邩�A��������Œ��͔��ɗ���ɂ��Ă��邱�ƂȂǁA�Ɩ��̏d�v�x���v���m�����B �����ĉ������S�ɋ������̂́A�䂪�����̗Y�قȉ������B���̎p�͗L�\�Ȑ搶�⍑�Œ��̕����q�����Ă���悤�Ɍ�����قǂɓ��X�Ƃ��Ă����B �s�j�b�̑f���炵���ƁA����͂��ׂĉ����E���̊F�l�̓w�͂̎����ł���Ƃ̂����t�́A�����Ղ��ꂽ�v���ł������B���߂ď��o���b�ŗ��m������������Ƃ��Ă��̏�ɂ���ꂽ���Ƃ��ւ炵���A���肪�����v�����B����w�̓w�͂����ď��o��v�̖��ɒp���ʂ悤�ɐ����������B ������č����C
����e������č����C �O�����C �s�j�b���C �d����E���㌴���v�u�s�j�b�V�X�e���v �ኴ �z�� ��������č����Ƃ������̂́A���ɖ@��ԗ����A��Ƃɕs���v�Ȃ��Ƃ��~�肩����Ȃ��悤�ɖȖ��ɍ쐬����Ă���̂��Ɛ[���������B�d����ɂ��ẮA�����߂ƁA�Г��ɂ�����`�[�N����������Ɠ����A���z�łȂ����Ă��邩����A����Ƃ��Ċm�F���邱�Ƃ���ł���Ƃ̂��Ƃ������B �č��̏d�_�|�C���g��(1)����̐^����(2)���������E���v�����m�ۂ��邱�Ƃł���B ���̂��߂ɂ��܂��͂��q�l�̑S�̑����悭�c�����A�e�Ȗڂ�O�N�ȑO�Ɣ�r���Ăǂ����ɂ������ȂƂ���͂Ȃ����A�]���Ȍo��͂Ȃ����A�ǂ��������藘�v�𑝂₹��̂����A�s�j�b�V�X�e����L�����p���Ȃ���o�c�v��ɖ𗧂ĂĂ��������B �፡��̔��W�� �č����ɂ́A�����ʂ̑����ɁA���ʏ탌�x���̃`�F�b�N�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ̂��Ƃ������B ���q�l�����f������ۂɂ͎��O�����ɗ͂����Ă��������B �����͍�Ƃ��C���[�W���Ă���̖K��ɂ��A�]�v�Ȏ�Ԃ͂͂Ԃ��A�o�c�̂��b���o����悤�ɁA�������l���čs�������B �����𗧂����邽�߁A�������͉������Ȃ���Ȃ�Ȃ����B
�u�В�����v�������Ɋ肤�d���̑��ʂ́w��{�I�ȏ����x�ł���v��{�I�ȏ����Ƃ́A �P�D��������č��Ŗ�����������Ǝ��Z�\���쐬�ł��邱�ƁB �Q�D��������Ђ̋Ɛт��A�ł��邾�������ɂ��߂�悤�ɂ��邱�ƁA �R�D��Ђ̋Ɛт𐔎��Ŕc��������A������A���Ԃ̌o�c���r�����邱�ƁA �S�D�ǂ��ɖ�肪����̂��A�������͂����邱�ƁA �T�D���P�̕K�v���������邱�ƁA �U�D��̓I�ȍs���Ɉڂ����� �V�D�s����̌��ʂ������邱�� �ǂ���A��������č����x�[�X�ł���B �s�j�b�Ȃ�ł͂̌o�c���͕\�⍕�۔��ۂ��g�����L���b�V���t���[�v�Z����}�\�ɂ������́A���̉�v�������Œ��悤�Ƃ�����A�c��Ȏ�ԂƔ�p��������悤�ȃT�[�r�X���A �����ږ◿�͈͓̔��łł���̂��A�I�[���s�j�b�Ȃ�ł͂̂��ƁI �� �l�����Ɛь�������s������ �I�[���s�j�b�Ŏ��v�������Ă���ΊȒP�ɂł���B �� ���Z���O�������݂��邱�ƂŌ��Z�\�����s���āA �������Z�Ɣ[�Ŏ����̏������o����B �� ���v�v����ł���̂ŁA�����J���\�Z��r�ȂǂŌo�c�v������Ă₷�����A �܂��Ɂw�����x�Ɩ���ԗ����Ă���Ɩ����o����B �ኴ �z�� �w�����x�Ƃ������Ƃ́A�č��S���҂̕K�{�\�͂́y���͗́z�ł���Ǝv���B �s�j�b�ɂ͌o�c���P�ɖ𗧂c�[�����������݂���B ���q�l�Ƃ��b������ۂɂ͑傢�Ɋ��p���A�œK�Ă�ł��o���Ă��������B ���q�l�͉������߂Ă���̂��A���̂��߂ɂ͂ǂ�������ǂ��̂��B ������O�̂��Ƃł͂��邪���S���ӁA�w�͂������B �፡��̔��W�� ���푽�l�Ȃs�j�b�V�X�e����m�邱�Ƃ����ł���B�A���i���炠���郁�j���[���J���A�o�c���P�ɖ𗧂v���O�����̑��݂��o���邱�Ƃ���n�߂����B �܂����q�l�̊�]���@�m����͂�g�ɒ����Ă��������B�v�_�����炳���A�I���i���Ă��b���������Ǝv���B �����̔O��Y�ꂸ�ɂ������B ���Q�U����
�ጤ�C���e���r�f�I���C�u�����ō�������v���������W�̃|�C���g ��������č��i�P�j�v ����č��͂Ȃ��K�v�� �č����ǂ��܂ōs���� ���q�l�̋Ɩ��̗���Ɗ֘A�쐬�؏� ����ʼn����ɂ�����TKC�̑Ή� TKC����ɂ��A�O�c�@���u�n�������@�v�C���Ĉꕔ ���q�l�K�⎞���ӓ_ �ኴ�z�� ����č��Ƃ́A����ɂ����ē`�[�ƌ��n�L�^���m�F���A�^������T�����邱�Ƃł���B��TKC�ђˉ�̂����t�����^�����M�d�ȃr�f�I�e�[�v�ł������B����č��͂��q�l�̓K���[�ł��m�ł�����̂ɂ��邽�߂ɓK���Ȏ�i�ł���A�������W���T�|�[�g���邱�Ƃ̂ł���A�d�v�ȋƖ��ł���B �č��̍ۂ͂��q�l�̋Ɩ��̗������������c�����A�������ׂ��߂�������ƕۊǂ���Ă��邩�A�ǂ����ɋ����͐����Ă��Ȃ������A����̃X�^�[�g����S�[���܂ł���{�̐��Ōq�����Ă���悤�ɖ��ĉ�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��BTKC�V�X�e���͏���ʼn����Ȃǖ@�߉����ɂ����S�Ή����Ă���̂ŁA����Ȃ��������������Ă���A���q�l�̊�Ɛ����̕ۏɂȂ�Ɗ������B ���q�l�̋Ɩ��̌n�𗝉����邱�Ƃ���ł���B�܂��͂�������n�߁A�ߏ��ނƓ`�[�̓ˍ����֔h�������Ă��������B���n�L�^�Ǘ��̏d�v�����펞�O���ɒu���Ă����B �s�j�b�̐搶���u���ꂩ��E�Ɖ�v�l�́A�č����o����l�ԂƏo���Ȃ��l�Ԃ̓�ɉ����Ă����v�Ɩ�������Ă����B���ۉ�v��ɐ������������{��v�ɂƂ�̂�����Ȃ��悤�A�w�͂��K�v�ł���B ���Q�T����
�ጤ�C���e���r�f�I���C�u�����ō�������v���������W�̃|�C���g�v �N�[�A�N���w���� �����w���̏d�v�� TKC�V�X�e�����p�̃����b�g �ߏ��ނ̕ۑ��A�t�@�C���A���� �������� �� �ኴ�z�� TKC�̃V�X�e���͗���ɗ����đg�܂�Ă�����̂ł��낤�ƍl���Ă������A�z���ȏゾ�����B�{���Ɂg�֗^���Ƃ̐������W�ɍv������A�@���ɏ��������V�X�e���h�ł������B �K�����q�l�ɂ��`�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂́A�`�[���N�[����̂͂��q�l�����g�ł���Ƃ������B��v����������s���Ă��܂��ƁA���̋L�^�͑��Ѝ쐬�Ƃ��Ĉ����A�@�I�ɏ؋��\�͂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �o�c��c�����邽�߂ɂ��A���q�l�ɋN�[���Ă��������K�v����[�����Ă���������悤�ɂ��b���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �ߏ��ނ̕ۊǂ����[�������A�~�����������ł����o����悤�ɂ��Ă����͓̂��R�ł��邪�A�����ݓ��Ɏ�茈�߂����Ă��Ȃ��ꍇ�́ATKC���i�̕��@�Ńt�@�C�����Ă����ƈ��S�E�m���ł���Ɗ������B TKC�͔��ɗD�ꂽ�V�X�e���ł���A������g�����Ȃ���ǂ�Ȃ��q�l�ɂł��A�K�����ŐV�̏������`���ł���Ǝv�����B�ł炸�ɏ������Ȃ�Ă����A�L�����p�ł���悤�ɂ������B ������Ɨ������������ŁA�N�[�A�N���̎w�����s���ׂ��ł���B ���Q�S����
�ጤ�C���e���s�j�b�E�����C�F��ؐM��搶 �u������A�Ɂv ������i����`�A���|���j�̊m�F���@ �I�����Y �ߏ��� �`�[���� �ኴ�z�� ���|���͔[�i���T�A�������T�Ɠˍ����A���|�����ו\�ƕ⏕��̊e�c������v���邱�Ƃ��m�F����B�������ɓ�������̂ȂǁA����ȊO�̍������Ȃ������m���߂�A�Ƃ̎��������B �������Ȗڕ��ނ��Ȃ��ƁA�c�Ɨ��v���Ȃǂɋ����������Ă��܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł���B �I�����A�\�Ȍ�����n�I�����s���ׂ��ł���B�ɊǗ���K���ɂ��A�������v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �ߏ��ނɂ��ẮA�������s�̂��̂͑S�ĘA�Ԃ�t���A���������̕����܂߂Đ������ۊǂ��Ă����B�܂��x���ؖ����◷��Z���̒��ӎ����A�c���^�⏑�ޔ͈͏ؖ����t�\�ȂǁA�l�X�ȏ��ނ̈Ӌ`�������Ă��������A��ϕ��ɂȂ����B �S�Ă̏��ނɂ��āA�K���֘A��������͂��Ȃ̂ŁA���ꂪ�ǂ����œr��Ă��Ȃ����A�����Ă��Ȃ��������ǂ��Ă��������B �ߏ��ނ͂��q�l������肷���ȏ؋��ł���̂ŁA�s���̂Ȃ��悤�A�������ۊǂ��邱�Ƃ��A�d�v�ƂȂ�B�`�F�b�N�ς݂̂��̂ɂ͎����Ǝ��̃`�F�b�N�}�[�N������ȂǁA������₷���H�v�����Ă��������B ���Q�R����
�ጤ�C���e������ ���������C�u�����Ǘ��A�����v �E�O���̓��t�̗̎����̎戵���i�ʏ팎�A���Z���j �E�N�[�̊ԈႦ�₷���|�C���g �E��������Ƃ� �E���Z���ɒ��� �E���q�l�Ƃ��b������ۂ̐S�� �E�Ŗ����̌��� �ኴ�z�� �O���̗̎����������ɍ��݂��Ă����ꍇ�A�ʏ팎�ł���A���ɏo�����ŋN�[���A���ۂ̎d�������̎����������ɂ��A���Z���ł���A�u�o��Ȗځ^�������v�ŏ������A���ۏo���������Ɂu�������^�����v�ŋN�[������B ���q�l�̔N�x�c�Ɛ��т�[�Ŋz�Ɋւ�邱�ƂȂ̂ŁA���Z������Ƃ����ė����̓`�[���m�F���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B �����Ƃ́A��Ђ̋��ɂ̂������w���Ă���A�a����|�P�b�g�}�l�[�����������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�N�[���t���܂߁A�l�����̈Ⴂ���N���₷���̂ŁA���������J�ɂ��`�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �Ŗ����͌o�����͎w�E���Ȃ����A����̘R��͌��d�Ƀ`�F�b�N���A�t�ѐł��ۂ����Ƃ���B �������A�������́A���v�ɉe���̂��邱�ƂȂ̂Ŕ�����o�����������m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �܂��A�l�Ԃ͒N���������������Ǝv���Ă���̂��Ƃ����B ���q�l�Ƃ��b������ۂɂ͂��̂��Ƃɗ��ӂ��A�C�����Q���悤�Ȍ����͐T�ނ悤�ɋC���������B ���Q�Q����
�ጤ�C���e�������a�����C�uTKC��v�l�̊�{���O�v �uTKC��v�l�͌��F��v�m�Ɛŗ��m�Ƃ����E�Ɖ�v�l�Ƃ��đ����A���҂̈�̉����w������W�c�ł���B�v �ኴ�z�� �uTKC��v�l�̊�{���O25���ځv�̒��̈�A�u���F��v�m����̉�����ɂ́A�ŗ��m��E�Ɖ�v�l�ł͂Ȃ��ƌ�������l�X�����邪�A����͊��S�Ȍ��ł���B���j��Ɍo�܂�����A�����Č��݁A�d��Ƃ�����v�w��̎����܂��ĐE�Ƃ����藧���Ă���_�ŁA���ɐE�Ɖ�v�l�Ƃ�����B���ɐO����Ԃ̊W�����A��̉����w�����ׂ������R�ł���B�v�Ƃ̂��Ƃ������B ����͏��a�̎���̎��ł���A���ꂩ��ŗ��m�͂ǂ�����ׂ��ł��邩�l��������ꂽ�B�Ⴂ����̐ŗ��m�������A�������A����ȏ�Ɍ��F��v�m�������悤�Ƃ��Ă��邱�̎���́A�������݂����l�X�Ȋp�x����l���˂Ȃ�Ȃ��B ���F��v�m�̎喱�͊č��ł���A�Ŗ@��m���ԗ����Ă���l�Ԃ͏��Ȃ��B�Ɩ��̖{�����S���Ⴄ�Ƃ����ӌ��������Ƃ�����B �F�X�ȕ������������g�Ŕ��f���A�s�����Ă����ׂɂ��ڑO�̂��Ƃɖv�������A������L���Ă����K�v������B �����ɌŎ������A���̎��X�ɍ��킹���Ή����o����悤�ȏ_��Ȏp���ł������B ���Q�P����
�ጤ�C���e���r�f�I���C�u���Z�č��̊�{�I�|�C���g�v ���Z�č��̎��O���� ����Ȗړ����쐬�̏��� ��������č����猈�Z�č��܂ł̗��� ���Z�č����̒��ӎ��� �ኴ�z�� �m��Ȃ����Ƃ���ŁA�ׂ��������Ƃ߂Ă����烌�|�[�g�p���V�����ɂ��Ȃ��Ă��܂����B �O��Ƃ��āA���Z�͂��q�l�����g���s�����̂ł���A��v�������͂��̊č��A�w������������ł���B�����͎����Ƃ��ĂƂ炦�A�X�s�[�f�B�[�ŗ��z�I�Ȍ��Z���s���ׂ��A�Ƃ̎��������B ���Z�č��̏����Ƃ��ẮA��������č����Ɂg���Z���������ꗗ�\�h�����q�l�ɂ��n�����A���Z�č��܂łɃN���A�ɂ��Ă����Ă��������A�Ƃ������ƂƁA�O���̊���Ȗږ������v�����g�A�E�g���A�����̐�����ԃy���ŏ�������ł��������A�Ȃǂł������B���Z�č����ɂ́A�p�ӂ��Ă������������������ɁA���Z�č����̊e���ڂɂ̂��Ƃ�A���𐳊m�Ƀ`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���̒m���s���〈���Ƃ��ɂ���āA���q�l�ɂ����f������������悤�Ȃ��Ƃ͐�ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�אS�̒��ӂ��Ċč����s���Ă����B���Z�č��ł͌�������č��ł͕�����ɂ��������ʔN�̊m�F���ł���ׁA��z�̔�p�����������Ă��Ȃ����A�s���R�Ȏx���A�������A�����Ă��Ȃ����ȂǁA�����I�Ƀ`�F�b�N���s�������B���ɐ؎��A���i���Ȃǂ̋����́A�s���Ȏ������ɗ��p����₷���̂œ��O�Ɋm�F����悤�ɂ���B ���Q�O����
�ጤ�C���e�����������C�u����č����̒��ӓ_�v �T�����쐬���A����̎���� �o�c�A�h�o�C�X�̎x���c�[�� �č��S���҂Ƃ��čs���ׂ����� �ኴ�z�� �T�����쐬�̍ہA���������͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �����̂��q�l�́A�a����Ɍ���ȊO�̂��̂��������Ă���̂ŁA�����E���o���Ă��������K�v�Ƃ̂��ƁB ����č��ɂ����ẮA�P�ɕK�v�Œ���̃`�F�b�N���s�����Z�\�����n������̂ł͂Ȃ��A���q�l�̌o�c�ɖ𗧂A�h�o�C�X�����邱�Ƃ���Ȃ̂��I�Ƃ������Ƃ��B���ꂪ���o��v�̋Ɩ��̕t�����l�����߂Ă���̂��Ǝv���B���̂��Ƃ��A���q�l�ɂ��Ɩ��i�����������Ă���������d�v�ȃ|�C���g�ƂȂ�B �w�W�E�����Ǝ�ʐR�����T��A�ŐV�̌o�c�w�W�A�e�w�̋Ɛѕ]����ʂȂǁA�s�j�b�Ȃ�ł͂̏��V�X�e�������p���āA�Ɩ����e�̌���ɖ𗧂ĂĂ����������Ƃ��K�{�ł���B ����̊m�F�́A�a����Ɋւ��S�Ă̎d���������A����ɊY��������z���}�[�J�[�őI�сA�W�v����B ����č����́A���O�̏����̈�Ƃ��āA���Ǝҏ��A�ƊE�ɂ����邨�q�l�̏�Ԃ̖ڈ��A�O�N�Ƃ̔�r�ȂǂׁA���P�Ă��l�������Ă����B�܂����i���炨�q�l�Ɋւ��Љ�I����V������s�b�N�A�b�v���Ă������Ƃ��s���Ă��������B ���P�X����
�ጤ�C���e���G���g���[���� �ኴ�z�� �����ւJ�ɋ����Ă��������A���肪���������B �i���ǂ������ĉ��������̂ŁA�ƂĂ��������₷�������B �ېŋ敪�̔�p�A���v���Ċm�F�ł��A�����ɑ��������e�������̂ŁA�����͏o�����B ���͓��e�̊m�F���������N���A�ɂ��Ȃ���̏������݂������̂ŁA���S�҂ɂ͂킩��₷�������B �E�����m�̃t�H���[���s���͂��Ă��鎖�������Ɗ������B �S�������͑̐����C�t���Ă����ۂ����B ����y���̎���킸��킹�邱�Ƃ̂Ȃ��l�A�w�߂Ă��������B �䂭�䂭�͎����t�H���[���Ă�����悤�ɂȂ肽���B ���P�W����
�ጤ�C���e�����������C ��p�A���v�̑Ή��W�i�a�^�r�A�o�^�k�j �ېŔ���ɂȂ�Ȃ�����Ƃ́H �ኴ�z�� �a�^�r�Ɏԗ����o�^�k �d�Ō��ہi�����ԐŁj �o�^�k �̔�������i�K�\������j �a�^�r �L���،� ���o�^�k ���z���� �a�^�r �o �� �� �ƁA�킩��₷�������Ă����������B�a�^�r�A�o�^�k�P�̂����ł������邱�Ƃ��o���Ă��Ȃ������̂ŁA����́A�Ȗڂ̔������R�A���ʂ��l���āA���X�̎�����m�F���Ă��������B�܂��A��{�I�ɇ@�ېŔ���̇D�ېŎd���A�B��ېŔ���̇G��ېŎd���ł���A�Ή��W��O���ɒu���˂Ȃ�Ȃ��B�ېň����ɂȂ�Ȃ����̂Ƃ��āA���i���A�e���z���J�[�h�Ȃǂ͇D��ېŎd�����B��ېŔ��ゾ�ƁA�m�����[�߂�ꂽ�B �����������������ɒ��͂���̂ł͂Ȃ��A�O��̗����Ή����鎖�ۓ����m�F������ŋƖ����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �������֘A�t���A���W�����čl����Ȃ�g�ɕt���Ă��������B ���P�V����
�u����č����C�v�O�����C�i�s�j�b�E�����C�j������č��̈Ӌ`�ƖړI ����v�������̋Ɩ��Ɗ֗^���Ƃ̋Ɩ��̋敪 ������č��O�̎��O�������� ������č�������������W ������č����̎g���� ����Ɩh�q���x ����č��Ƃ͊֗^���N13��K�₵�A��v�����̐^�����A���ݐ��A�ԗ������m���߂邱�Ƃɂ���āA��v�L�^�̓K�@���A���m���A�y�ѓK�������m�ۂ��邱�Ƃ��o����A�Ƃ̂��Ƃ������B���͂����̂܂ܓǂނ̂ł͂Ȃ��A �m�F �� �m�� �� �w�� �Ƃ����悤�ɓǂނ̂��Ƌ����Ă����������B ����̌v��ɂ��Ă��d���Ƃ̑Ή��W��c�����A��������������Ă��邩�ƍ��m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŗ������邱�Ƃ�������A�܂��͂��q�l�̋Ɩ���A�̗���܂�����Ŋč��A�w�����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƌ����Ă����������B ���q�l�����f������O�ɁA�s���͂Ȃ����A�h�莖���͂�����ƃN���A�ɂ��Ă��邩�ȂǁA�\���Ɋm�F�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �M���W��z����ŁA�܂��͎��₳�ꂽ���Ƃɐ��������J�ɓ����A���m�ɏ����A�������ɑ��k�A�܂��͎w�������Ȃǂ��āA����T�d�ɍs�Ȃ��Ă��������B ���P�U����
�u���������C�w����ŇB�x�v �����ƊO���̈Ⴂ�͒N�ɑ��ĘJ���̑Ή����x�������A���ꂪ��Ƃɑ��Ă��ǂ����ɂ���ĕς��Ǝv���Ă������A�Ⴆ�Α�H������l���Ǝ�ł���A�x�����͉ېŎd���ɂȂ�Ƌ����Ă����������B �O����Ƌ����̋�ʂ͍ٔ��ɂȂ��������ł���ƔF�������B �O���̓`�[�������Ƃ��Ɂu�O����ƂɎx�����Ă���v�Ƃ��������łȂ��A�u�O���́�������ƂƂ����A�~�~�~���_�A�Ή��̎x���������`�[�v�Ƃ����������������B �܂������Ɋւ��Ă���ЂɐӔC�����邱�Ƃ܂��ă`�F�b�N�������B ���P�T���� �u���������C�w����ŇA�x�v���ł̕K�v�� ���萔���E�z�����Ȃǂ̎�舵�� �ł������̎Y�Ƃ���邽�߂̂��̂Ɣ��R�ƒm���Ă͂������A���ꂪ�ǂ��̍��������Ă�����̂Ȃ̂��͑S���m��Ȃ������B�܂��Ă�ېŋ敪��55�i�A���d���j�ł���ȂǁA�ӎ��������Ƃ��Ȃ������B ���ȏ���ł́g�w�����ɂ��������萔���͌����ɎZ������h�ƏK���Ă͂������A������ʼn��߂Ď���������ċ����Ă����������B �ԈႦ��Ƃ��q�l�ɂ����ւ�Ȃ����f�����������邱�ƂɂȂ�̂ŁA��ɏ����ɋ^��������Ȃ��琳���������������B ���q�l�̍w������������Ȃǂ�����ۂɂ͊ԈႢ�v��Ȃǂ͂Ȃ����A���������łȂ������A�������ɂ����k���āA���m�ɏ������Ă��������B ���P�S���� �u���������C�w�o�L�x�v���}���V�����w�����̓`�[�̏����� ���@���ǂ̎葱 �}���V�����w�����ɂ́u���� �^ ���� �v�̒P���Ȏd��ł͂Ȃ��A�����ɓy�n���w�����Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƌ����Ă����������B �܂��@���ǂ͏��Ɠo�L�ƕs���Y�o�L���s���Ă���A���Ƃ̊J�n�A�I���ɂ͏��Ɠo�L���K�v�ł���B ����͑�O�ҋ@�ւƂ��Ă��̉�Ђ��ؖ�����A�Ƃ̂��Ƃł���J�Ɠ͂��Ƃ͂܂��ʂł���Ƌ����Ă����������B�������Ă����̂Ő������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �`�[���`�F�b�N����ۂɂ͉����s�����Ȃ����A�B��Ă��镔���͂Ȃ��̂��������Œ��ׁA���̂����ŏ����A�������ɒm�������Ă��������A���q�l����������v�������s���Ă��邱�Ƃ��m���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���P�R���� �u���������C�w�`�[�����E���Z���菇�x�v�������E�z�����������̓`�[�̏����� �����q�l���ȖڊԈႢ���������̓`�[�N�[�̎w���̎d���A�����̎d�� �����Z�菇�ƌ��Z�̃`�F�b�N�|�C���g ���������̂悤�� �u���ʗa�� �^ ��旘���i���z�����j�~�~�~�v �Ƃ��邾���ł͂Ȃ��A�����ɂ�20%�̐ŋ����B��Ă���̂��Ƌ����Ă����������B�܂��A�Ȗڂ��C������ۂ���x����̓`�[���}�C�i�X�œ��͂���悤�ɁA�Ƃ������Ă����������B ���Z���ɂ͂s�o�r1000�̑O�c��M�̌�A�u����ł̉ېŋ敪�ʏW�v�\�v�̏o�͂���ɁA�������p���ׂ�������A�����lj���p���Ȃǂ��s���Ă��Ȃ��������q�l�Ɋm�F���Ă��瑼�̏����Ɉڂ�悤�ɁA�Ƃ̂��Ƃ������B �`�[�N�[���ɂ́A�s�j�b�V�X�e���ɍ��킹��������̋N�[�𐳂����s���悤�ɒ��ӂ��Ă��������B ���Z���ɂ͎��Ԃ̂�����\���̂���O���m�F�������ɃN���A�ɂ��A���̑������ɍs���悤�ɂ���ȂǁA�������l���ď����������B �������p���ׂ͎��Y�ʂɎ擾�N�����A�o�^�m�n�Ȃǂ��`�F�b�N���邱�Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɂ������B ���P�Q���� �u���������C�w����Ň@�x�v���ېŎ��Ǝ҂̋敪 ���݂Ȃ��d���� ���[�łɍ��킹���a���A��v���� �ېŎ��Ǝ҂̍s���Ă��鎖�Ƃ��A���̎d���̓��e�ɂ���āA�T��ށi�Ǝ�ʂɂP��`�T��j�ɕ��ނ����Ƃ������ƂƁA���̐��藧���������Ă����������B �܂��e�ېŎ��Ǝ҂̔[�Ŋz���A���ۂɐ����Ă͂߂Čv�Z���Ă�������A�悭���������B ����ł̔[�Ŋz�͍��z�ɂȂ邱�Ƃ������̂ŁA����ł̔[�Ŋz�����Z���A���̌��z�����u�d�Ō��ہ^��������Ł~�~�~�v�Ŕ�p�v�サ�Ă������Ƃɂ���āA��萳�m�Ȏ��Z�\���쐬�o����A�Ƃ̂��Ƃ������B�܂����z���P�N�����̒���a���ɂ��Ă������Ƃɂ���Ĕ[�Ŏ��ɍQ�Ă��ɂ��݁A��s����̐M�p�x���オ��A�ƃ����b�g�܂ŋ����Ă����������B���ۂɁA�����̂��q�l�ł́A�[�ŏ����̂��߂ɁA��������ϋ���[�ŏ����a��������Ă����Ђ�����Ƃ̂��Ƃ������B ���q�l�̔[�ł���A���Ђ���Z�@�ւ���̐M�p��������悤�Ȃ��Ƃ͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B �[�łɑ��Ă͍אS�̒��ӂ��ċƖ����s���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���P�P���� �s���C���e�t�u���������C�w����v�Z�x�v ������̎��یv�Z ���ٗp�ی����ɑ��鏊���ŁA�ٗp�ی��̉ېŁE��ېł̌��� ���������O �s���z�t ��������Ă�������������̌v�Z���@�𗝉��o���Ă��Ă悩�����B���߂ĕ������̎w���͂Ɋ��ӂ����B �ٗp�ی����̌������Ŗ@�ɂ��Ⴄ���Ƃɋ������B�������邽�߂ɂ͊e�Ŗ@�̊�{�ʔO���w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���㎊���`�Ƃ������t�������Ă����������B���㍂�ɂƂ��ꂸ�������v��Nj����A�����̗ǂ��Ɩ����s���悤�Ɏw�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���X�̐����̒��ŁA���̓X�͂Ȃ��ׂ����Ă���̂��A�Ȃ��ׂ����Ă��Ȃ��̂��A�l�C�̗��R�͉��Ȃ̂��A�ǂ�����悭�Ȃ�̂����A�l���Ă��������B ��ɋ^��_��T���A���P���������Ȃ����A���q�l�Ƃ̂��Ƃ�Ɋ����������B ���P�O���� �s���C���e�t�u���������C�w�[�t���̏������x�v ���[�t���̏����� ������ł̌v�Z �s���z�t �����m����c��܂��Ă����������B�[�t�����悭����ƐF�X�Ȃ��Ƃ������Ă���A��������ƌ��邱�Ƃ̑厖�������߂Ċ������B �����̌���̂����݁A�v�Z����b���狳���Ă��������A�����ւ肪���������B �\�������邾���ʼn�ЂɂƂ��ăv���X�Ɍq��������A�܂��\�������Ȃ����������ő傫���}�C�i�X�ɂȂ����肷��̂ŁA���q�l�̏��悭�������A�����ω�����������ɓK�����Ώ��@��ł���悤�A�w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���X���� �s���C���e�t�u���������C�w�a�^�r �����x�v �������̏d�v���A�m�F���@ �����ۗL���Ƃ��ꂪ�������Ƃ��̂��q�l�ւ̓`�B���@ ���`�[���L���̒��ӓ_ �s���z�t ���������킹��Ƃ������Ƃ́A�����̂͊ȒP�����m���ɍs���̂͂Ȃ��Ȃ�����Ƃ̂��Ƃ������̂ŁA���ꂩ�疈���������̌����c�����킹�Ă������ƂŎ����o����Ǝv���B�������g�ł��̓����Ɋ����������ŁA���ꂩ��̂��q�l�Ƃ̂��Ƃ�ɖ𗧂ĂĂ��������B �č��Ō���������Ă���ƁA�d���Z�œ��̑ΏۂɂȂ��Ă��܂��Ƌ����Ă����������B �����Ƃ͌��������ł���B�܂��͍����̂�������m���Ȉ�������g�ɕt���Ă��������B ����16�F15�Ɏ��������ɂ̌������������킹�邱�ƂɂȂ����B�C�����ɐ������`�F�b�N���A�`�[���Əƍ������Ă��������B ���W���� �s���C���e�t�u�r�f�I���C�w���Z���̍����E�ǂݕ��E���������x�v �����Z���Ƃ͉��� �����Z���쐬�̎菇�A�֘A�\�t�g�A ���s�j�b�V�X�e�� ���o�c���� �s���z�t ���Z���Ƃ͊�Ƃ̌��N��Ԃ�\���o�����[�^�[�ł���A�Ƃ̂��Ƃ������B���m�Ȍ��Z�����������Ɍ����悭�쐬���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ��J������ł���Ŗ����A���Z�@�ցA����Ɂu���S�Ȋ�Ƃł���v�Ƃ������S����^���邱�Ƃ��o����B���m�Ȍ��Z���쐬�͉�v�������̎g���ł���A���̂��߂ɂ�������̃`�F�b�N�͌������Ȃ��ƍl��������ꂽ�B �����������Z����p���Ă�������ƌo�c���͂����A���q�l�Ƃ��b�����Ȃ��痈���ȍ~�Ɍ����ĉv�X�v���X�ɓ]����悤�ȕ��@�������Ă��������B ���Z�����������߂邾���łȂ��A��Ɂu�Ȃ�����͂����Ȃ̂��v�u����͑O���Ɣ�ׂĂǂ��Ȃ̂��v�u�ǂ�����������Ɨ��v�̊l���Ɍq���邩�v�Ȃǂ��v�Ă��Ă��������B �����{�o�험�v���A���{��]���ȂǁA�o�c�ɖ𗧂�����A���q�l�̔��W�Ɍ��т������B ���V���� �s���C���e�t�u���������C�w���Z���E�d��x�v �����Z���̕K�v���A�p�r ���d��̈Ӗ� �s���z�t �w�K��͒m�邱�Ƃ̏o���Ȃ��A�����ɂ����Ă̊�{�I���y��I�Ȏ����������Ă��������A�����ւ肪���������B ���Z���́u���Q�W�҂ɑ��N�x�̌o�c���т��������߂̂��́v�ƍl���Ă������A����͑��ƌ����̊w�K�p��ł���A���{�̑命�����߂钆����Ƃɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��B���Z���⎎�Z�\�́A���q�l���o�c���P�����邽�߂̈�̎�i�ł���A�ʐM��Ȃ̂��Ƃ̂��ƂŁA���Ȃ炳�ꂽ�B �܂��d���������O�̂悤�ɍs���Ă������A�u�L���ł���v�Ƃ����A���߂ē��X�̉�v�����������ȑf���A�W�v���Ă�����̂Ȃ̂��ƍl���������Ƃ��o�����B ���Z���⎎�Z�\����ɂ����ۂ́A�K���O�N�����Ɣ�r���A�ڍׂɕ��͂���B����ɑ��Ďd���A��p�͂ǂ��ω����Ă���̂��A�ǂ������_�͂Ȃ��̂���ǂݎ��A���q�l�ɂ��`�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �܂��`�[�N�[���͂T�v�Q�g��O���ɂ����A����̂Ȃ��悤�ɂ��Ă����B ���U���� �s���C���e�t�u�r�f�I���C�w����č��̊�{�I�|�C���g�T�x�v ���č��̗���A���O�������m�F���� ��v�������E���݂̍���A��v������������Ă͂����Ȃ��T�[�r�X ����č��̕K�v�� �s���z�t ����č����s�����Ƃɂ���āA���q�l�����S�o���邱�Ƃ���ł���B �������w�������A���k���o����Ƃ��������b�g�������Ă����������Ƃ��M���W��z�������Ō������Ȃ��B ���̂��߂ɂ����O�̏����͕s���̖����悤�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�d�b�A����ӂ炸�A�h�莖���̊m�F���Y��Ȃ��悤�ɂ���B��v�p�i�s���̗L���ȂǁA�ׂ₩�Ȕz�����K�v�ƂȂ�B ���q�l�̓`�[���N�[���Ȃ��A�t�@�C�����O�����Ȃ��ȂǁA���܂�Ă����ӂ������Ă��f�肵�Ȃ���A���q�l�����g�̐������W�Ɍq����Ȃ��Ɗ������B �I�m�ȏ����A���m�ȏ������q�l�ɗ^������悤���͂������B���̂��߂ɂ���{�I�Ȏ����A�K����m�F�Ȃǂ̏����͂�������s���A���ޕs�����͕K���Ȃ��悤�ɂ��A���̂����Ŋč��ɗՂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �܂����i���炨�q�l�ɖ𗧂悤�ȎЉ�I����������Ă��������B ���T���� �s���C���e�t�u���������C�w�������p������Ɩ@�l���Z�\���V�X�e���ɂ��āx�v ��H19�N�x4��1���ȍ~�̌������p��x�����ɂ��� ��������Ж������^�̑��v�s�Q�����x�̉��� �����[�X����̈����ɂ��� ���@�l���ƊT�����̗l������ ���L���b�V���t���[�\�̍��Ə����Ή� ���n���� �ŗ����� �s���z�t �������p��x�������������߁A���N�x4��1���ȍ~�J�n���ƔN�x�̂��q�l�ɂ��Ă͒��ӂ��K�v�ł���B�c�����i���T������1�~�ɂȂ�A�ȑO�Ɏ擾���Ă������Y�ɂ��Ă��ΏۂƂȂ�̂ŁA�V�����v�Z���@��K�p���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���{�I�x�o�ɂ��Ă��ʎ��Y�Ƃ��Ĉ����Ă������ƂɂȂ����B�悭�����A���K�������ɔ��f�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �V�K�Ƀ��[�X�_������킵���ꍇ���A���ؗ��ōς܂��Ă������̂���������ɕς�邱�Ƃ��玑�Y�v��ƂȂ�A�������p��̔����⏞�p���Y�łɂ��ւ��ȂǁA��X�̂��Ƃ܂ōl������K�v������B �V�X�������������x���ʂȂǂ��J��Ԃ��ǂ݁A���ɂ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���[�X��g�ꍇ�͕K���_�����������āA�ǂ�ȃ��[�X�_��Ȃ̂����悭�c�����A����ɑ������������s���Ă������Ƃ��厖�ł���B ���S����
�s���C���e�t�u�r�f�I���C�w��v�������̋Ɩ��Ƃ́x�v ����v�������̋Ɩ� ���s�j�b�V�X�e���̊T�v ���Ɩ���̒��ӓ_ �Ȃ� �s���z�t ��Ƀv���ӎ��������Ƃ������厖�ł���Ǝv�����B ���X�̉�v�Ɩ��Ɏ�����ƂȂ��A���͏����A�`�F�b�N���s���Ƃ����̂͂������A���q�l�ւ̌��t�����A�����A�Ȃǂ���������ƍs�����Ƃ���ł���B ���q�l���������₪�������Ƃ��ɂ͂���������ɑ��������A�����A�������ɑ��k����ȂǁA�T�d�ɍs�Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �u�r�f�I���C�w�L�т鎖�����̐E�����x�v ���E��ł̃}�i�[�A���A�p���A������ ���h�����̊�{�A���ނ̓n�����A�d�b�̎�莟�� �Ȃ� �s���z�t �Љ�l�̊�{�I�}�i�[�K�ł��ėǂ������B �܂��A���܂łT�v�P�g�Ƃ������t�͒m���Ă������A�g������Łh����������T�v�Q�g�Ƃ������̂͏����ł������B ��肪�������Ă�������Ɏ���܂łɂ��Ȃ�̎��Ԃ�v����ۂɂ́A������ƒ��ԕ�����ȂǁA������O�ɍs���Ă������Ƃɂ��Ă����߂đ�����m�F�o�����B ���ߏ��̐����ƕۑ��ɂ��Č��C ���s�j�b�V�X�e���̑�����@�̌��C
���ߑO�X�����炨���܂��s���C���e�t �@�\�Ɉ��������h�r�n�l�t�@�C�����w�B �ߌ�P������ߌ�T���܂� �s���C���e�t ���ߏ��̐����ƕۑ��ɂ��Č��C�����B ���s�j�b�V�X�e���̑�����@�̌��C�����B �s���z�t �܂��A�������̂͗̎��̈����̒��J���ł��B �Ȗڂ��Ƃɓ��t���ɕۊǂ���Ƃ��������ł͂Ȃ��A �ԍ���t���Ă��ꂢ�ɓ\��A���₷���`�ɂ��Ă���̂Ɋ��S�����B ���q�l���̎������ɕۊǂ��Ă���̂��悭�킩�����B �̎��������ł͂Ȃ��A���낢��ȏ��ނɑ��Ă̈ӎ��̍����������������B �s�j�b�V�X�e���̑�����@�̌��C�����B �u�G���g���[�v�Ƃ����������Ŏg���V�X�e���̓��͕��@�̌��C���B �s�j�b�̓��̓V�X�e�����g���ɂ����Ƃ͊����Ȃ������B ���͂��`�[�`���̉�ʂŕ�����₷���A�ꗗ�`���̉�ʂ͌��₷�������B �����Ȗڂ�A�����Ďg���Ƃ��͂d���������L�[�ŕ\�������̂ŁA���肪�ǂ������B ��������c ���G���g���[���͋Ɩ� �ߑO���͎������́u������c�v�B�s��c���e�t ������c�ł́A�����̌��C�\��i��u�\��҂ƌ��C���e�j�̊m�F�A �O��̌�����c�ł̐\�����莖���̊m�F�A �e�l���̋��猤�C�v��A �������̖ڕW�B���x�̊m�F�A ���q�l�̌�������č��⌈�Z�i���̊m�F�A �ڋq�����i�q�A�����O�j�ɂ��āA�č��S���҂��炨�q�l�̂��ӌ��̒��� �����A���Z���{�̌������A �h�L�����[�N�X�g�p���̒��� �� �s���z�t ���ɂ��ă��x���������A�v���ӎ��̍����������ł���Ɖ��߂Ďv�����B�������A�S�Ăɂ����ĉ��P�_��T���A���q�l�ɖ𗧂���������Ƃ����p�����S���ɂ���A���S�����B �ߌ� �s���C���e�t �u�G���g���[���͋Ɩ��v �s���z�t ���q�l�����g���d���o���Ɩ����悭�������Ă���������A�Ƃ������z���������B����ȖڊԈႢ���Ȃ��A���͂��₷�������B �h�R������Q��A�ʂ̓��Ɉ����������������Ƃ��ɁA�܂Ƃ߂ĂP��̎d��ł����Ă����̂ŁA�����̎c�����r���ł���Ă��܂��Ă����B ��͂�N�[�́A����������Ƃ��Ȃ�������Ȃ��ƍĔF�������B ���ߏ��̐����ƕۑ��ɂ��Č��C ���s�j�b�V�X�e���̑�����@�̌��C
���ߑO�X�����炨���܂��s���C���e�t �@�\�Ɉ��������h�r�n�l�t�@�C�����w�B �ߌ�P������ߌ�T���܂� �s���C���e�t ���ߏ��̐����ƕۑ��ɂ��Č��C�����B ���s�j�b�V�X�e���̑�����@�̌��C�����B �s���z�t �܂��A�������̂͗̎��̈����̒��J���ł��B �Ȗڂ��Ƃɓ��t���ɕۊǂ���Ƃ��������ł͂Ȃ��A �ԍ���t���Ă��ꂢ�ɓ\��A���₷���`�ɂ��Ă���̂Ɋ��S�����B ���q�l���̎������ɕۊǂ��Ă���̂��悭�킩�����B �̎��������ł͂Ȃ��A���낢��ȏ��ނɑ��Ă̈ӎ��̍����������������B �s�j�b�V�X�e���̑�����@�̌��C�����B �u�G���g���[�v�Ƃ����������Ŏg���V�X�e���̓��͕��@�̌��C���B �s�j�b�̓��̓V�X�e�����g���ɂ����Ƃ͊����Ȃ������B ���͂��`�[�`���̉�ʂŕ�����₷���A�ꗗ�`���̉�ʂ͌��₷�������B �����Ȗڂ�A�����Ďg���Ƃ��͂d���������L�[�ŕ\�������̂ŁA���肪�ǂ������B ���o���b�ŗ��m�������������� ���h�r�n�̌��C�����B�ߑO�X�����炨�����͂���Ōߌ�Q���܂��s���C���e�t �h�r�n�K��̌��C �h�r�n�l�t�@�C���i�h�r�n�̎������K�肪�l���ɗp�ӂ���Ă���j��ǂ�Ō��C�B���ɂh�r�n�錾�A�v���Z�X�̌n�}�A����č��A���Z�Ɩ��𒆐S�Ɋw�B �s���z�t �̐��̐������A�F�߂�ꂽ�������ł���ƍĔF�������B�Ɩ��̑S�Ăɂ��čH�����ƂɒS���ҁA�菇�����L����A�֘A�������ނ̊Ǘ����@�܂Ŗ��m�ɒ�����Ă��ċ������B �Ŗ����ւ̒�o�A�܂��͏����֒�o����܂ł̃v���Z�X���A�O�ꂵ�ă~�X��h���悤�ɂȂ��Ă���A���A���q�l�̉�Ђ����P�Ɍ��������߂̘b�������܂ł�����Ă���Ă����B �ߌ�Q������T���܂� �s���C���e�t �����o���b�ŗ��m�������̂T�����̓`�[���́A�`�F�b�N�A �����ɁY �F�����̒��댻���c���Ƌ��ɂ̌����Ƃ̓ˍ��A����\�L�� �s���z�t ���͏����ɂ��Ă͓��ɓ���͊����Ȃ��������A���X�̌����Ǘ��̐��������Ă��邱�Ƃ�A�`�[���k��Ȃ���������ƋL�����Ă��邱�ƂȂǂɋ������B ���͏I����A�������Ɍ������ۗL���Ƃ̓ˍ��̏d�v���ɂ��ċ����Ă��������A�����ւ���ɂȂ����B�܂��A�����̗т���ɂƂĂ����J�ɋ����Ă��������A���肪���������B |